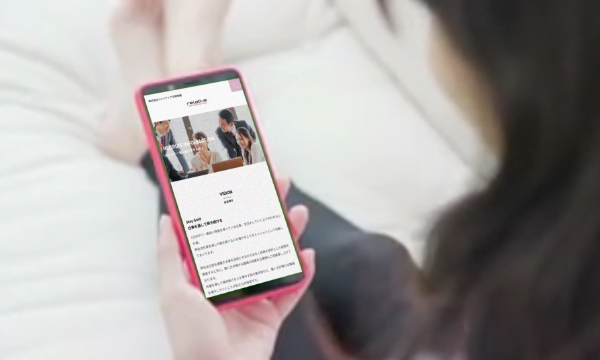お知らせ Information
採用ニュース
労働基準法「40年ぶりの大改正」“働き方”はどう変わるのか
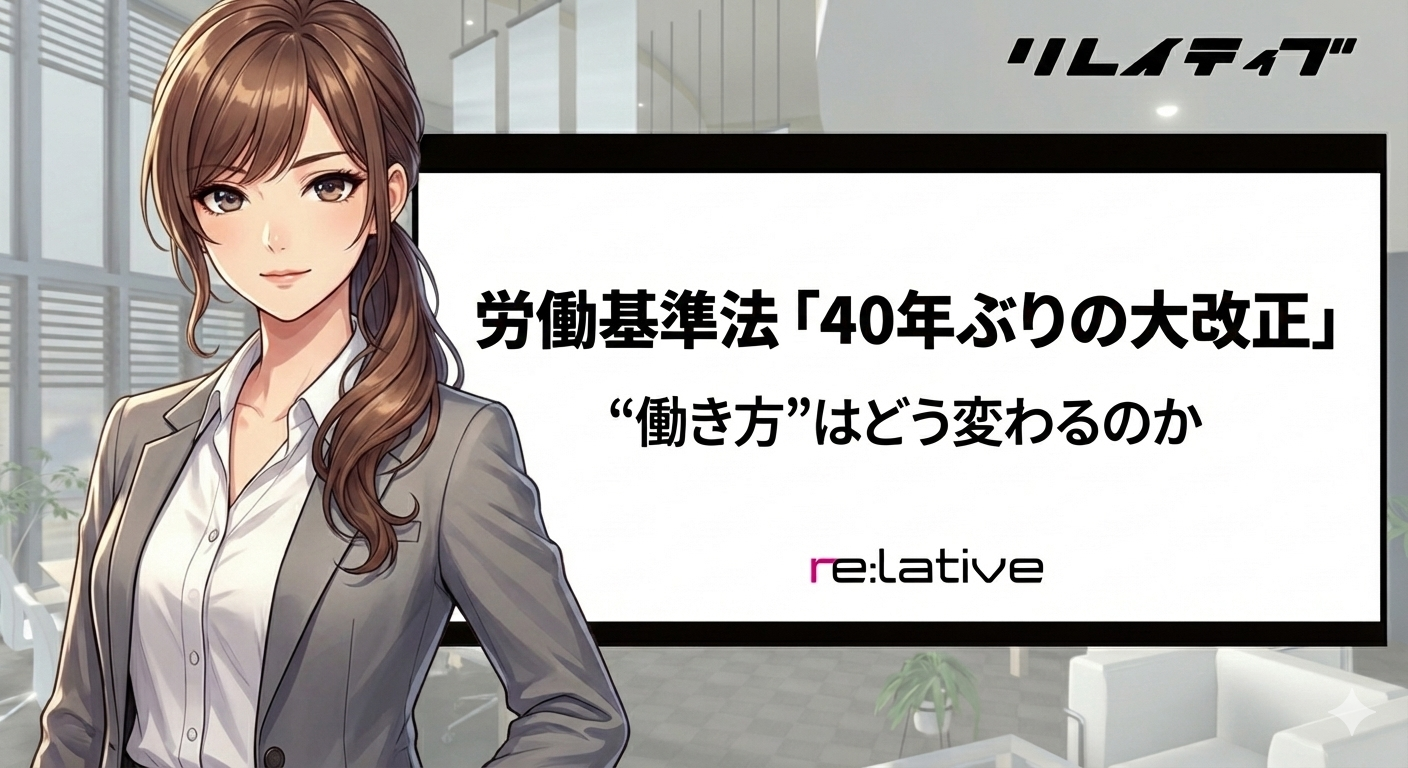
「労働基準法が40年ぶりに大改正される」この言葉を聞いても、多くの経営者や人事担当者にとっては、まだどこか実感の湧かない話かもしれません。
しかし今回の見直しは、単なる条文修正や規制強化ではなく、これまで当たり前とされてきた“働き方”そのものを問い直す動きです。
背景には、働き方の急速な変化があります。
テレワークやシフト制の高度化、副業・兼業の広がり、業務委託やフリーランスの増加などにより、働く時間や場所、契約の形は大きく多様化しました。
一方で、労働時間の管理や健康確保が個人任せになりやすく、長時間労働や心身の不調、離職や労務トラブルが後を絶たないのも現実です。
今回の「40年ぶりの大改正」と言われる議論では、「どこまでが働かせすぎなのか」「会社はどこまで働く人の健康に責任を持つべきなのか」「多様な働き方をどのように制度として守るのか」といった、根本的な問いが投げかけられています。
連続勤務の上限や勤務間インターバル、時間外の連絡ルール、管理職の健康確保、副業時代の労働時間管理など、いずれも現場でグレーなまま運用されてきた領域が、見直しの対象になりつつあります。
現時点では法律がすでに改正されたわけではありませんが、変わろうとしている方向性は明確です。
本記事では、労働基準法の改正議論を制度解説にとどめず、「これから会社の“働き方”はどう変わるのか」「人事・経営として何を考えるべきか」という視点で、分かりやすく整理していきます。
なぜ今、「労働基準法の大改正」が議論されているのか
労働基準法が制定された1947年。
当時の働き方は非常にシンプルでした。
・働く場所は工場や事務所
・働く時間は朝から夕方まで
・働き手はフルタイムの正社員が中心
・仕事と私生活の境界は明確
しかし現在はどうでしょうか。
テレワーク、フレックスタイム、副業、シフト制、プラットフォームワーク。働く「場所」「時間」「契約形態」は細分化され、労働時間の管理や健康確保が個人任せになりがちになっています。
実際、精神障害による労災認定は増加傾向にあり、「法律は守っているはずなのに、なぜ不調者が出るのか」という問いに、従来の労基法では答えきれなくなってきました。
今回の見直しは、「長時間労働をどう減らすか」ではなく、「そもそも持続可能な働かせ方とは何か」を制度側から再定義しようとする動きだと捉えると理解しやすいでしょう。
「働かせすぎない」仕組みへの転換
今回の議論で、最も企業実務に影響が大きいのが連続勤務・休日・勤務間インターバルに関する見直しです。
改正後は連続勤務は「13日まで」が上限になる可能性があります。
現行制度では「4週4休」という考え方があるため、理論上は長期間の連続勤務が可能です。
しかし、実態として、連勤が続いた結果、心身に不調をきたすケースが後を絶ちません。
そこで検討されているのが、「14日以上の連続勤務を原則として禁止する」という考え方です。
これは飲食・小売・介護・宿泊・運送など、シフト制で“人が足りない時に連勤で埋める”運用をしている業界ほど影響が大きい内容です。
今後は、「忙しいから仕方ない」「本人が希望しているから問題ない」では通らなくなる可能性が高いでしょう。
もう一つの大きなポイントが、勤務間インターバルが“努力義務”から“前提条件”に変更することです。
退勤から次の出勤まで、十分な休息時間を確保するという考え方ですが、これまで多くの企業では「余裕があれば導入するもの」という扱いでした。
今後は、夜遅くまで残業したにもかかわらず翌朝早くから出勤する働き方や、深夜のトラブル対応を行った後も翌日を通常勤務として扱うといった運用そのものが、制度の観点から見直しの対象になっていくと考えられます。
企業にとっては一時的に負担が増えるように感じられるかもしれませんが、見方を変えれば、これまで慣習的に行われてきた業務の詰め込み方や無理のあるスケジュールを見直すための、一定の強制力が働くとも言えるでしょう。
「見えない労働」をどう扱うか
今回の議論のもう一つの軸が、“見えにくい労働”をどう制度で捉えるかという点です。
「つながらない権利」という言葉の背景には、チャットツールやスマートフォン、SNSの普及があります。
これらのツールによって業務のスピードや利便性は飛躍的に向上しましたが、その一方で、勤務時間外であっても仕事から完全に切り離されにくい状態が、知らず知らずのうちに常態化してきました。
ただし、ここで議論されているのは、業務連絡を一切禁止するといった極端な対応ではありません。
求められているのは、
・どこまでが緊急か
・誰が対応するのか
・対応した場合、どう扱うのか
こうしたルールを、個人任せではなく組織として決めることです。
ルールがない状態は、「未払い残業の温床」「ハラスメント認定リスク」「管理職の疲弊」を同時に生みます。
「つながらない権利」とは、社員を守るための制度であると同時に、会社を守るための設計でもあります。
これまで暗黙の了解で許容されてきた「管理職だから時間は自己管理」という考え方も、見直しの俎上に載っています。
特に問題視されているのが、「権限はないが肩書きだけ管理職」「業務量は一般社員以上」「健康管理は本人任せ」という“名ばかり管理職”の構造です。
今後は、管理職であっても、健康確保のための仕組みは会社責任という考え方がより強まるでしょう。
多様な働き方を前提とした制度へ
副業・兼業、業務委託、フリーランスなど雇用の形が多様化する中で、労基法も「正社員前提」からの脱却を迫られています。
現在は、副業先を含めて労働時間を通算し、割増賃金を計算する必要があります。これが副業解禁の大きなブレーキになっていました。
検討されているのは、「健康管理のための時間把握は維持」ただし割増賃金の計算は、各社ごとに完結させるという方向性です。
これは企業側にとっては実務負担の軽減になりますが、同時に健康管理責任はより重くなることを意味します。
また、プラットフォームワークの拡大により「契約は委託だが、実態は雇用に近い」ケースが増えています。
今後は、指示の出し方、拘束時間、評価・ペナルティの有無などこうした点がより厳しく見られる可能性があります。
“安く使えるから委託”という発想は、中長期的には経営リスクになり得ます。
今後会社が取るべき対応策
労働基準法の「40年ぶりの大改正」と言われる今回の議論を受けて、人事・経営に求められるのは、法改正の行方をただ待つ姿勢ではありません。
重要なのは、すでに示されている方向性を踏まえ、自社の働かせ方を段階的に見直していくことです。今後の対応策は、大きく分けて三つの視点に整理できます。
①「働かせすぎ」を前提にしない運営への転換
連続勤務や長時間労働に頼る体制は、今後ますます通用しにくくなります。
まずは自社で、連勤が常態化している部署や、退勤から次の出勤までの間隔が極端に短い働き方がないかを可視化し、業務量や人員配置、シフトの組み方を見直すことが重要です。
これは法対応というより、持続可能な現場運営を実現するための基礎作りと言えるでしょう。
②「見えない労働」を放置しない
時間外の連絡や突発的な対応、管理職の長時間労働など、これまで個人の裁量や善意に委ねてきた部分について、会社としてのルールを明確にする必要があります。
どこまでが業務で、どのような場合に対応が必要なのかを整理し、属人化した働き方を減らしていくことが、将来的なトラブル防止につながります。
③多様な働き方を前提とした制度設計
副業・兼業や業務委託の活用が進む中で、労働時間管理や健康確保の考え方もアップデートが求められます。
契約形態にかかわらず、過重な働き方になっていないかを把握し、必要に応じて運用を見直す姿勢が重要です。
これらの対応は、すべてを一度に行う必要はありません。
重要なのは、「変わる前提」で小さく着手し、徐々に整えていくことです。
今回の労働基準法見直しを、単なる法令対応ではなく、自社の働き方と組織運営を見直す機会として捉えることが、これからの人事・経営にとって大きな差を生むポイントになるでしょう。
労働法改正についてご不明点やご相談したいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。