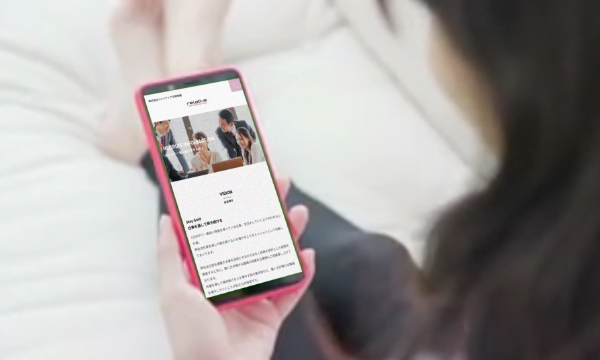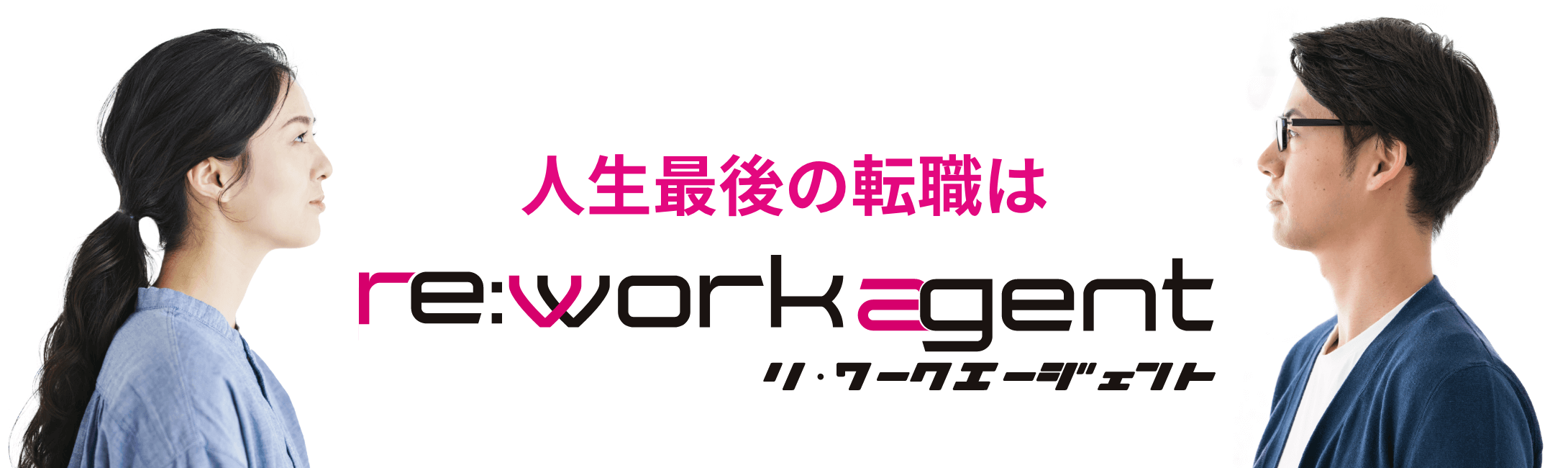お知らせ Information
採用ノウハウ
【人事・経営者必見】リテンションの重要性と戦略的アプローチ
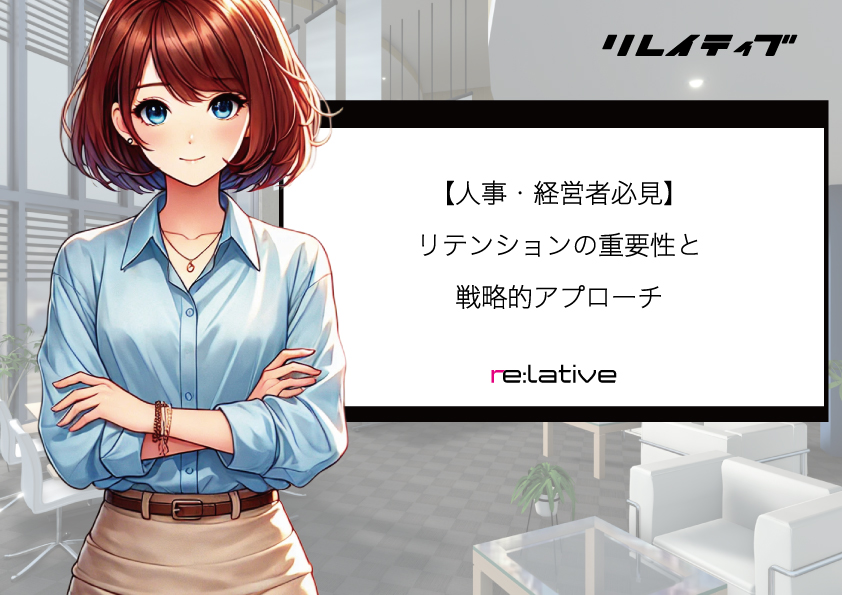
近年、日本企業を取り巻く人材環境は大きく変化しています。労働人口の減少、有効求人倍率の上昇、働き方の多様化に伴い、採用市場はかつてない競争状態にあります。
こうした中で「優秀な人材を採用する」こと以上に重要視され始めているのが リテンション(Retention)=従業員定着 です。採用に多額のコストをかけても、入社した社員が短期間で退職してしまえば、そのコストは水泡に帰します。それだけでなく、業務の引き継ぎ負担、残された社員のモチベーション低下、顧客対応品質の低下など、目に見えにくい損失も膨らみます。
本記事では、経営層・人事担当者の視点から、リテンションの重要性と具体的な実践方法を体系的に解説します。
リテンションとは何か
リテンション(Retention) とは、企業が優秀な従業員を長期的に維持・定着させるための取り組みや施策を指します。
単に離職率を下げるだけでなく、社員が組織に愛着を持ち、最大限のパフォーマンスを発揮できる状態をつくることが目的です。
採用活動は「入口戦略」、リテンションは「出口戦略」ではなく「中間戦略」です。
入社後の社員を育て、活かし、活躍し続けてもらうためには、採用とリテンションは一体で考える必要があります。
リテンションへの注目が高まる背景には、明確な統計があります。
まず、新卒の3年以内離職率を見ると、高卒では38.4%、大卒では34.9%という高水準が続いており、この傾向は統計上の最高値に近い状況です。特に高卒においては、就職直後の1年目に16.7%が離職し、初期離職が全体の離職を大きく押し上げています。
リテンションの重要性
— 数字で見るインパクト
厚生労働省の調査や民間企業の試算によれば、新卒1人あたりの採用コストは平均50〜100万円、中途採用では1人あたり100〜150万円かかるとされています。
さらに教育・研修コスト、OJTの生産性低下分を加えると、1人の即戦力化までに総額300〜500万円以上の投資が必要です。
このコストを回収する前に退職されれば、企業にとっては大きな損失です。例えば、年商10億円規模の企業で、従業員50人、年間離職率20%の場合、毎年10人の採用・育成コストが発生します。これが年間3,000〜5,000万円規模の固定的な負担となり、利益を圧迫します。
リテンションの主な施策領域
リテンション向上には、単発の施策だけでなく 総合的・継続的なアプローチ が必要です。ここでは大きく6つの領域に分けて解説します。
1. 報酬・福利厚生
給料やボーナスを市場水準に合わせ、成果に応じたインセンティブを用意します。健康支援や自由に選べる福利厚生など、社員の生活をサポートする制度も整えます。
・市場水準に見合った給与体系
・業績連動型のインセンティブ
・柔軟な福利厚生(カフェテリアプラン、健康支援)
2. キャリア開発・成長機会
社員が成長できる道筋を示し、希望に沿ったキャリアパスを用意します。研修や資格取得支援、メンター制度などでスキルアップを後押しします。
・社員の希望に沿ったキャリアパス設計
・定期的なスキルアップ研修
・メンター制度やコーチングの導入
3. 職場環境・人間関係
安心して働ける職場をつくります。ハラスメントを防ぎ、意見を言いやすい雰囲気を作ること、上司のマネジメント力を高めることが大切です。
・ハラスメント防止
・風通しの良い社内コミュニケーション
・上司のマネジメントスキル向上
4. エンゲージメント施策
社員が会社に愛着を持てるようにします。意見を反映するアンケートや社内イベント、表彰制度を活用し、経営陣がビジョンを共有して共感を生みます。
・社員の意見を反映する仕組み(従業員サーベイ)
・社内イベントや表彰制度
・経営層のビジョン共有と共感形成
5. 柔軟な働き方
テレワークやフレックスタイムなど、時間や場所を選べる働き方を整えます。育児・介護との両立や副業も支援し、ライフスタイルに合った働き方を可能にします。
・テレワークやフレックスタイム
・育児・介護と両立できる制度
・副業解禁による自己実現の支援
6. データ活用
勤怠やアンケートのデータを分析し、離職の兆しを早くつかみます。部門ごとの課題を明確にし、AIを使って予測精度を高めます。
・離職予兆分析(勤怠データ、エンゲージメントスコア)
・部門別・属性別の離職率トラッキング
・AIによるパフォーマンス予測
リテンション向上には、計画的で継続的な取り組みが必要です。まずは離職率や退職理由をデータで把握し、部署や職種ごとの課題を特定します。そのうえで、短期施策(給与や待遇の改善、面談制度など)と中長期施策(キャリアパス整備、研修制度、企業文化の改善)を組み合わせます。
実行後は離職率や従業員満足度を定期的に測定し、効果を検証しながら改善を続けます。このPDCAサイクルを回すことで、一時的な離職抑制ではなく、長期的に社員が働き続けられる環境を構築できます。
リテンション成功事例
事例1:IT企業A社
【対象】
従業員数300名規模のWebサービス系企業。20〜30代のエンジニア・デザイナーが中心で、離職率は20%と業界平均より高め。
【施策】
全社員を対象に毎月1回の1on1面談を実施。上司と部下が仕事やキャリア、悩みを率直に話せる場を制度化。また、面談内容をもとに業務改善やキャリアパス修正を迅速に反映。
【結果】
3年間で離職率が20% → 8%に低下。採用・教育コストを年間約2,000万円削減。社内アンケートで「上司への信頼度」が25%向上。
事例2:製造業B社
【対象】
地方に拠点を持つ精密部品メーカー。従業員約150名。若手社員の定着率が低く、技術継承が課題。
【施策】
熟練技能者を「技能マイスター」として認定し、若手とペアで作業するOJT制度を導入。技能マイスターには教育手当を支給し、評価制度にも反映。
【結果】
若手の定着率が2年で65% → 88%に改善。不良率も15%減少し、生産性が向上。技能継承により新製品開発スピードも向上。
事例3:小売業C社
【対象】
全国展開するアパレルチェーン。店舗スタッフの離職率が高く、特に入社1年以内の退職が多かった。
【施策】
入社後3カ月間のメンター制度と、キャリア相談窓口を導入。新人は先輩社員が業務だけでなく職場適応もサポート。キャリア相談は匿名でも利用可能に。
【結果】
入社1年以内の離職率が35% → 18%に半減。スタッフ満足度調査で「職場の安心感」が大幅向上し、売上も前年比5%増加。
経営層が押さえるべき視点
1. 採用コスト以上の価値
新たに人材を採用するには、求人広告費、面接・選考の時間、入社後の教育コストがかかります。中途採用では1人あたり100〜150万円、新卒採用では50〜100万円が目安です。加えて教育期間の生産性低下を含めると、1人あたり300〜500万円以上の投資になります。
つまり、優秀な人材が1年でも長く働けば、その分だけ採用・教育コストを削減でき、利益率も向上します。
2. 企業ブランドへの影響
高い定着率は社外からの信頼にもつながります。「働きやすい会社」としての評判が広がれば、採用活動も有利になります。逆に離職率の高さは口コミやSNSで広まり、採用力低下につながります。
3. 社員エンゲージメントの向上
リテンション施策は、単に「辞めない」状態をつくるだけでなく、社員が会社に誇りを持ち、意欲的に働く状態(エンゲージメント)を高めます。これにより、生産性やイノベーションの創出力が向上します。
4. 短期的経費削減ではなく中長期投資
経営判断として重要なのは、リテンションを「人件費削減のためのコストカット」としてではなく、「人材資産への投資」と捉えることです。短期的には制度整備や研修などの費用がかかりますが、中長期的には採用コスト削減、生産性向上、企業ブランド強化という形で大きなリターンが得られます。
リテンションは採用よりも投資効果が高い場合があります。人材採用には多額のコストがかかりますが、定着率が上がればその削減効果は大きく、利益率の向上にも直結します。また、高い定着率は企業ブランドを強化し、「働きやすい会社」としての評判を広げ、採用活動にも好影響を与えます。さらに、社員のエンゲージメント向上にもつながり、生産性やイノベーション創出力を高めます。短期的な経費削減ではなく、中長期的な人材投資としてリテンションを捉えることが経営判断の要となります。
リテンションは、単に「辞めさせない」ための施策ではなく、社員一人ひとりが会社で働く意味を見出し、長期的に貢献できる状態をつくる戦略的取り組みです。
採用難が続く今、経営層・人事が最優先で取り組むべき課題の一つであり、企業の存続と成長を左右する重要テーマです。