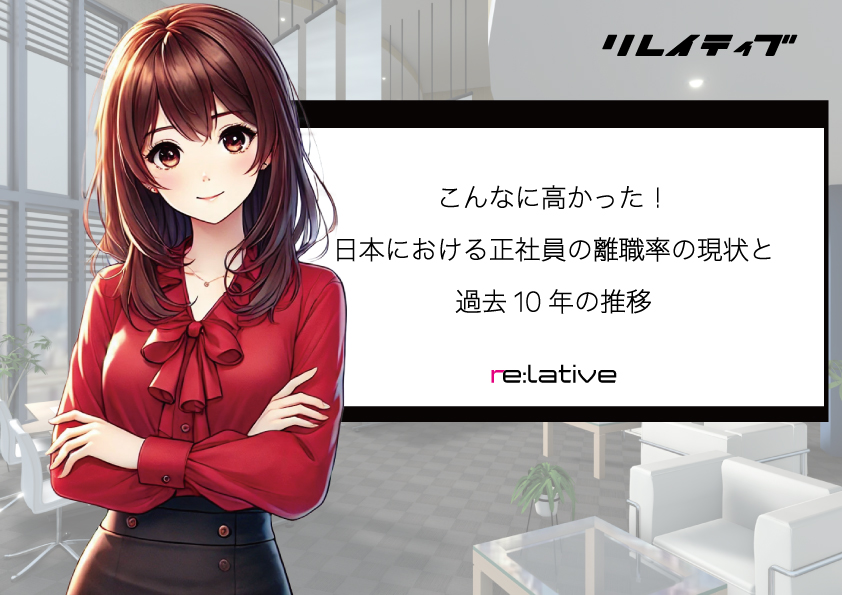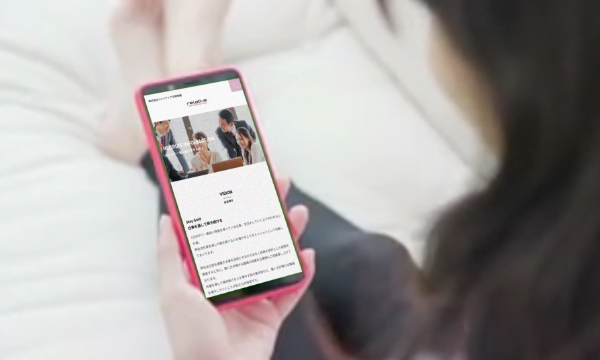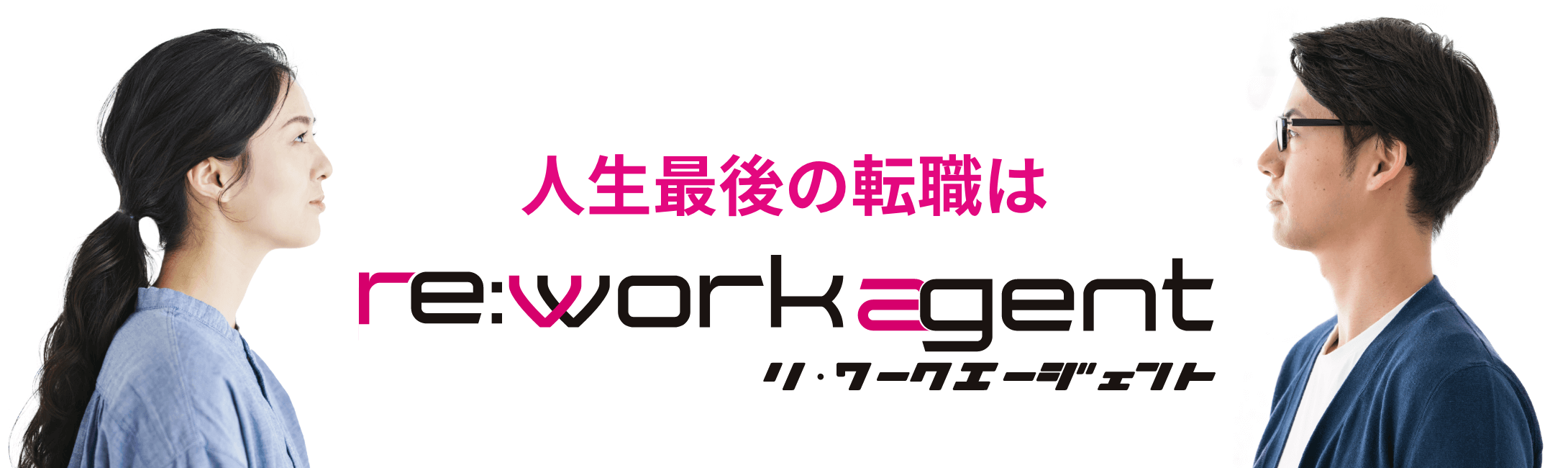お知らせ Information
採用ニュース
こんなに高かった!日本における正社員の離職率の現状と過去10年の推移
正社員離職率の基本とその意義
日本企業における正社員の離職率は、経済状況や労働環境の変化、働き方改革の進展とともに大きな注目を集めています。昨今の日本では、少子高齢化や人手不足、ワークライフバランスの意識の高まりなどの要因により、正社員の離職率に変動が見られ、企業の人材戦略に深刻な影響を与えています。過去10年間の離職率の推移を背景に、離職率がどのような要因で変動してきたのでしょうか。
離職率は、ある期間内に退職した従業員の割合を示す指標です。厚生労働省の「雇用動向調査」では、離職率は以下のような式で求められています。
離職率(%)=(一定期間中に離職した労働者数 ÷ その期間中の平均就業者数)× 100
この定義では、自己都合・会社都合・定年退職など、期間内に会社を離れたすべての労働者が「離職者数」に含まれ、期間中の平均就業者数は通常、期間開始時と終了時の就業者数の平均値を用いて計算されます。
過去10年間の離職率の推移
2010年代の初頭、バブル崩壊後の景気回復が進む中で、正社員の離職率は10%前後と比較的低い水準にありました。企業は安定した経済成長を背景に、長期雇用を前提とした労働慣行が根強く残っていました。多くの企業では「終身雇用」の文化がまだ色濃く、若手社員の定着率も高い傾向が見られました。
2015年〜2019年、働き方改革や経済環境の変動や企業の評価制度改革が進む中で、求職者自身のキャリア志向がより明確になり、転職市場が活発化し、この頃から、離職率は12%前後と緩やかに上昇する兆候が見られるようになりました。
2020年以降は、新型コロナウイルス感染症の影響でリモートワークや働く環境の見直しが急務となったこと、また企業文化や働き方への期待が多様化したことから、近年は離職率がさらに上昇しているケースが報告されています。特に、2021年以降は、経済の回復局面とともに転職市場も活発化し、13~14%と上昇し、2024年では15%近い水準に達しているとする調査もあります。
過去10年間の推移から、日本の正社員の離職率は、従来の終身雇用の慣行から成果主義、そして働き方改革やリモートワークの普及など、さまざまな要因により徐々に上昇傾向にあることが分かります。特に、働く環境の多様化や個人のキャリア志向の変化、企業文化の改善に向けた取り組みの必要性が叫ばれる中で、企業は定着支援策や働きやすい環境の整備、公正な評価制度の構築など、さまざまな施策を講じることで離職率低減に努めることが求められています。
離職率が高い会社の特徴
離職率が高い会社には、いくつか共通する特徴が指摘されています。以下は、主な要因や具体例になります。
1. 長時間労働と過重な業務負荷
・毎月残業時間が極端に長く、月100時間を超えるケース
・休日出勤が常態化している部署があり、定時で帰ることがほとんどできない
・業務量が人員に見合わず、納期や目標達成のために社員に過度なプレッシャーがかかる
これにより、社員は慢性的なストレスや疲労、健康問題を抱え、最終的には転職を検討する傾向があります。
2. 不透明な評価制度とキャリアパスの欠如
・昇進や昇給の基準が曖昧で、どのような成果が評価につながるのかが分からない
・同じ成果を上げているにもかかわらず、上司によって評価が大きく異なるケース
・キャリアパスが明確に提示されず、将来の成長や自己実現の可能性が感じられない
このような状況では、頑張っても報われないという感情が蓄積し、社員が他社でのチャンスを求める動機付けになります。
3. 低い給与水準と不十分な福利厚生
・同業界の平均給与より大幅に低い給与体系
・年次昇給やボーナスの見込みが乏しく、成果を反映した報酬制度がない
・社会保険、退職金制度、育児休暇などの福利厚生が充実しておらず、ライフプランに対する安心感が得られない
給与や福利厚生の低さは、生活の安定を求める社員にとって大きな不満材料となり、転職を検討する大きな要因となります。
4. コミュニケーション不足と管理体制の問題
・上司との定期的な面談がなく、フィードバックや相談の機会が乏しい
・組織内の情報共有が不十分で、経営方針や会社の将来像が社員に伝わっていない
・パワーハラスメントやセクシャルハラスメントが横行しており、問題が上層部に報告されても対処されない
こうした環境では、社員が孤立感を感じたり、不安や不満が蓄積しやすく、結果として離職率が上がる傾向があります。
5. 企業文化と価値観のミスマッチ
・トップダウンの強い企業文化で、社員の意見が尊重されず、改善提案が反映されにくい
・企業理念やミッションが現実の業務と乖離しており、社員が自分の価値観や働く目的を見出せない
・変革が求められているにもかかわらず、古い慣習や風土が根強く残っており、柔軟な働き方やイノベーションが推奨されない
企業文化が自分に合わないと感じる社員は、より自分の価値観に合致する職場環境を求めて転職する傾向があります。
以上にように、離職率が高い会社は、労働環境、評価制度、給与・福利厚生、コミュニケーション、そして企業文化といった複数の要因が重なり合っているケースが多いです。各企業は、これらの具体的な問題点を改善することで、社員が安心して長期間働ける環境を整え、結果的に優秀な人材の定着と企業の持続的な成長につなげることが求められます。
市場流動性の高まりと新たな働き方
労働市場のグローバル化や多様な働き方の浸透に伴い、今後も正社員の離職率は一定以上の水準を維持する可能性が高いと考えられます。企業は、単に離職率の数値を下げるだけでなく、変化する労働市場に対応した柔軟な人材戦略を策定する必要があります。社員一人ひとりのキャリアパスや働く意欲に寄り添いながら、長期的な組織の発展を実現するための環境整備が求められます。
現代の労働者は、収入のみならず、働く上での自己実現や社会貢献、そしてライフワークバランスを重視します。企業は、こうした労働者の価値観に応じた企業文化の再構築を行い、柔軟かつ魅力的な職場環境を提供する必要があります。離職率の低減は、単に数字を下げる施策に留まらず、社員が安心して長く働ける環境をいかに作り上げるかが問われる時代です。
今後も労働環境の変化は続くと予想されるため、企業は現状の課題を正確に把握し、柔軟かつ戦略的な人材マネジメントに取り組むことが必要です。各企業が、社員の働きがいやキャリア形成を重視し、安心して長く働ける環境を整備することが、ひいては全体の離職率低減と企業の競争力向上につながるでしょう。